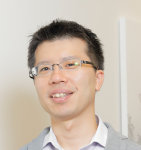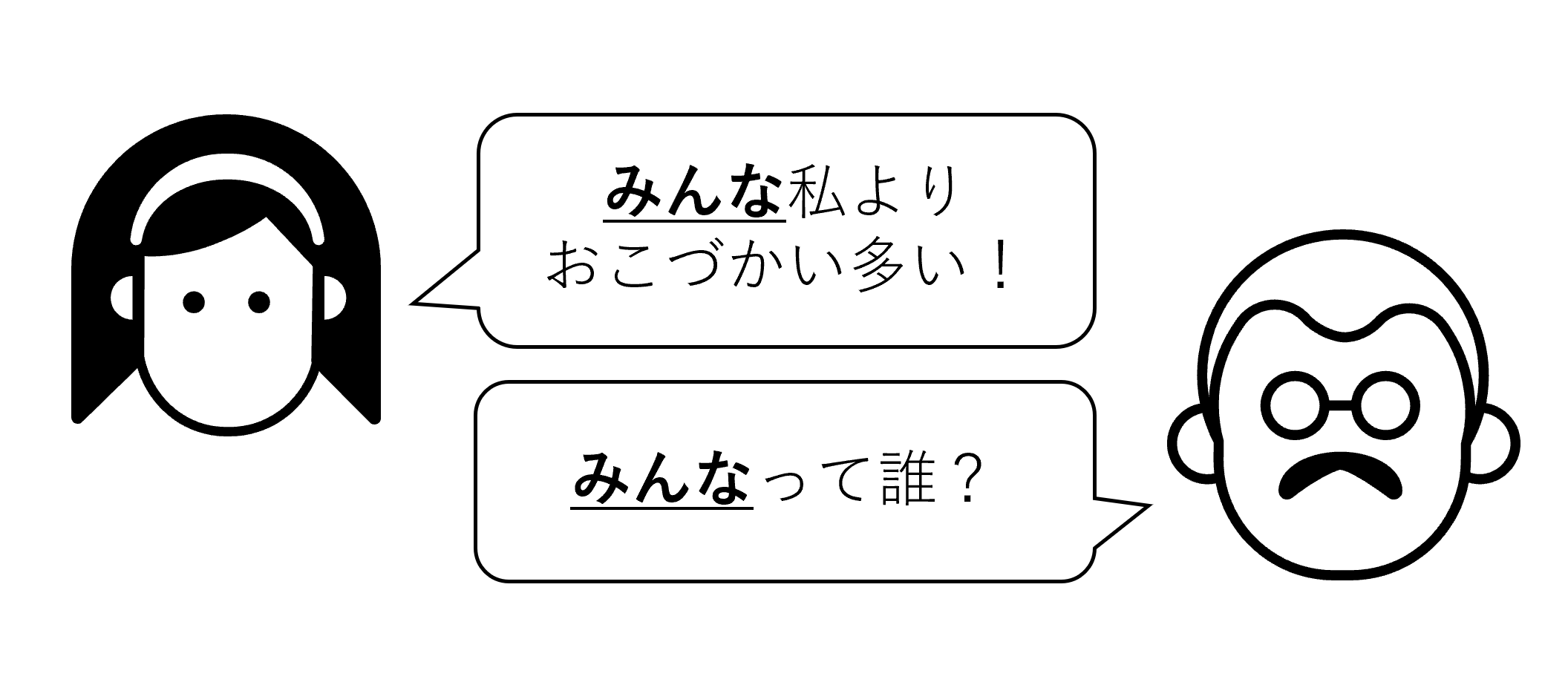社会におけるデータ活用の拡大に伴い、データ活用人材の需要はますます大きくなってきています。東京理科大学データサイエンスセンターとSAS Institute Japan 株式会社は、データサイエンス人材の教育とキャリアについての知見を深めるため、2022年12月21日(水)に合同でシンポジウムを開催しました。本記事では、このイベントの様子をご紹介したいと思います。 シンポジウムの開会にあたり、東京理科大学 副学長 坂田 英明 様、SAS Institute Japan 株式会社 営業統括本部長 宇野 林之からご挨拶がありました。坂田副学長は、2031年に150周年を迎える東京理科大学が掲げるTUS Vision 150のなかで、データサイエンス教育に重点を置いていることに触れ、2019年に設置された東京理科大学データサイエンスセンターが、データサイエンスの応用分野創造と人材育成を進めていることを紹介しました。SASの宇野からは、40年以上の間、アナリティクスを専業としてきたSASの歴史に触れながら、リソース不足で実りが少なかった第二次AIブームと違い、昨今の第三次AIブームは豊富な計算リソースを背景に社会に浸透しており、特にビジネスの世界では、データドリブン経営から業務のディシジョンのサポートまで、データサイエンスが幅広く活用されていることを紹介しました。両者ともにデータ活用人材の不足を課題に挙げ、本シンポジウムでの議論に期待を寄せました。 第1部:東京理科大学におけるデータサイエンス教育 第1部では、東京理科大学のデータサイエンス教育の紹介と、そこで学んだ学生からの研究発表が行われました。 まず、データサイエンスセンター長 矢部 博 様から、データサイエンス教育の取り組みについて紹介がありました。理系の総合大学である東京理科大学では、各学部でデータを活用した研究・教育がされてきましたが、学長直下の組織として設置されたデータサイエンスセンターが横串となり、各学部や教育推進機構、研究推進機構、産学連携機構と連携しながら、データサイエンス教育・研究のハブとしての役割を果たしています。 政府はAI戦略2019のなかで年間50万人のリテラシーレベルの人材と年間25万人の応用基礎レベルの人材の育成を目標に掲げていますが、東京理科大学では、既に2019 年度から独自の教育プログラムを展開しています。まず、全学部生が対象のデータサイエンス教育プログラム[基礎]は、数学、統計学、情報学、データサイエンス、その他の授業から20単位をB評価以上で取得することで、認証書が授与されます。大学院生が対象のデータサイエンス教育プログラム[専門]では、数理コース、ビジネスコース、人工知能コース、医薬コース、機械学習コース、医療統計コース、Informaticsコースの各コースが設定する科目から8単位をB評価以上で取得することを要件としており、高度な知識と技能を持った学生を認証しています。 また、SASとの共同認定プログラムであるSAS Academic Specializationでは、SASを活用したデータ分析を実践する授業の6単位を取得することで、SASスキルと統計解析の知識を認定します。特に、SASソフトウェアを用いた研究課題や実践課題に取り組み、論文を提出し、審査に合格することが条件となっています。このような教育プログラムをデータサイエンスセンターが提供することで、各学部での一般・専門教育と並行してデータサイエンス人材の育成を推進しています。 次に、理学部第二部数学科 教授 伊藤 弘道 様から、社会人履修証明プログラムについて紹介がありました。東京理科大学の理学部第二部は、日本唯一の夜間理学部として、特に理科・数学を中心とした学び直しの機会を提供してきました。現在、社会人学生の割合は1割程度で、教員免許の取得を目指す学生も多く在籍しています。学部の課程と並行して履修証明プログラムを2020年度から開始しています。コースの種類としては、SAS認定コース、データサイエンスコース、数理情報コース、統計学入門コース、数理モデリングコース、数学リテラシーコース、微分幾何入門コースがあり、さまざまなスキルや知識を持って社会で活躍できる人材を育成しようとしています。 続いて、SAS教育の実践を含む教育の一つとして、大学院講義「カテゴリカルデータ解析」に関し、工学部情報工学科 教授 寒水 孝司 様より紹介がありました。この授業は理論と演習から構成されます。演習パートについて、企業で活躍する専門家が講師として招聘され、担当しています。講師の統計解析への知見、SASプログラミングの専門的な知識や技術を吸収しようと、学生は理論の学習と演習課題に交互に取り組んでいます。特にこの授業では、クロス集計とその指標の推定から、交絡のあるデータを扱うための技術を習得します。 学生の研究発表 第1部の最後に、4組の学生からデータ分析を活用した研究発表がありました。独自に設定した課題について、大学のプログラムで提供されているデータや自身で収集したデータを用いた分析結果を発表しました。みなさん、基礎分析をしっかり行い、データの傾向を掴もうとしていたことが印象的でした。将来の夢の発表もあり、スキルを磨いて夢を実現されることを期待しています。 第2部:ビジネスにおけるデータサイエンス人材の活用 第2部では、ビジネスにおけるデータ活用事例およびデータ活用人材のニーズやキャリアについて、講演がありました。 採用市場におけるデータ活用人材のニーズ まず、株式会社マイナビ 就職情報事業本部 マイナビ編集長 高橋 誠人 様より、データ活用人材の採用市場におけるニーズについて紹介されました。株式会社マイナビは、就職活動支援サービスの提供のみではなく、大学や企業と連携してデータ活用人材の育成の支援を行っています。特に、2024年卒業学生向けの新卒就職活動サイト「マイナビ2024」からは、「DX(デジタル・トランスフォーメーション)がわかる超基礎講座」というe-learningを提供し、IT人材のキャリア形成を支援しています。 講演では、経済産業省の「新産業構造ビジョン」や情報処理推進機構の「DX白書2021」などからデータを引用しながら、IT人材のニーズについて論じました。ほぼすべての分野においてIT技術を核とした革新が期待されているなか、IT人材の需要は高まることが予測されています。米国ではIT人材不足が解消されてきている一方、日本国内のIT人材は質・量ともにまだまだ不足感があります。プロダクトマネージャー、ビジネスデザイナー、テックリード、データサイエンティストと、さまざまな側面のデータ活用人材が不足していると感じている企業が半数以上です。(一方で、「自社には必要ない」と考えている企業も2割程度あるのも問題かもしれません。)2030年には、中位シナリオで45万人のIT人材が不足すると予測されています。マイナビ社の調査結果を見ると、新卒の就職市場は全体的に堅調であるなかで、情報系学生の就職先が製造・ソフトウェア・通信分野に偏っていることが問題であるように思われます。転職市場では、全体と比較してIT・通信・インターネットの分野において、転職による給与の上昇が期待できるようです。最近では、経験者を募集する割合が減ってきていることも人材不足を反映しているかもしれません。